はいこんにちはー。当サイト:カラスクの日誌管理人のカラスクです。今回は、久しぶりに物語形式の文章を書いていきます。
暇ならどうぞ。ちなみに動画版も存在します。
第一章 最初の記憶
僕は、3歳の時から人の終わり方を知っています。
突然ですが画面越しのそこのあなた。一番古いは何ですか。生まれて、最初に記憶したものは何ですか。
僕の最初の記憶は、2歳だったころ。母方のおばあちゃんの家での出来事です。僕は、おばあちゃんの家のリビングに入る扉の陰に隠れていました。おじいちゃんを驚かせようとしたのです。
そわそわしながら、待っているとき。おじいちゃんがリビングに入ってきました。その瞬間に僕は、「ワっ!」と大きな声をかけると、おじいちゃんは、驚くことなく、持っていた入れ歯を僕の顔に近づけてきました。
きっと外からでも、隠れているのが見えていたのでしょうね(笑)。
僕は、入れ歯の勢い、というか入れ歯の恐怖に負け、驚いてひっくり返りました。
これが僕の持っている一番古い記憶です。
第二章 白いベッド
僕が3歳になった頃でしょうか。おじいちゃんは、寝ていることが増えました。白い天井、白いベッドの上です。そして決まって、おじいちゃんに会うときは、おばあちゃんと家族全員で行っていました。
ある日、葉っぱが色づく季節だったでしょうか。またおじいちゃんに会いに行くと、ベッドの上にボンタン飴というお菓子が置かれていました。僕は、お菓子に目がなかったので、食べようとしました。
すると、いつも優しくて、温厚なおばちゃんの怒鳴り声が聞こえました。
「それは、おじいちゃんのだから、食べちゃだめ!」
僕は、涙目で、ボンタン飴をそっと戻そうとすると、秋に似つかわしくない、暖かい風が吹きました。
「いいよ。たべな。」
おじいちゃんは、僕にいってくれました。
僕は、「やったー」と目じりが下がり、ボンタン飴の箱を開けました。残りは、あと2つだったので、1つだけ食べました。
第三章 いし、とい、こつ
またある日のことです。上着を羽織って外に出るような季節のこと。
また家族全員とおばあちゃんでおじいちゃんに会いにいきました。そのとき、みんな静かに、おじいちゃんが機械に入れられているのをみていました。僕は、何だかよくわからないけど、楽しそうだと思いました。
だから、「ぼくもおじいちゃんのところいくー」と雪原に1輪咲く花のように場違いな声で言いました。すると、父親が僕の腕をガシッとつかみ、「みてはいけない」とえも言わさぬ声をだしました。
父親は、僕の頭を自分の方に向けました。僕は、目の端でおじいちゃんが機械に飲み込まれているところをみていました。おじいちゃんは、あお向けて、目をつぶっていました。静かな、寝顔でした。
場面は、変わり、気付けば行列に並んでいました。学校の教室よりやや広い部屋だったと思います。黒い人たちがいます。みんな一人一人、何やらツボの中に石を入れていました。ごつごつと歪な形をした石です。
列が進み、僕と父親の番が来ました。父親が1つ、石を入れると帰ろうとしました。しかし…
「ぼくもやるー」と駄々をこねました。
よく分からないけど、やってみたかったのです。子供の好奇心でしょうね。
僕は、父親に抱えられながら1つ、トングのようなもので石をツボに入れました。石の表面は、火山の石のようにざらついていますが、3歳の力でも容易に持ち上げ、入れることが出来ました。大きさに見合わない重さだったと記憶してます。
しばらく時間が経ったのか、次の日なのか。すっぽりと記憶がありません。気づけば、まだ霧の濃い朝。お墓の前にいました。そこで、知らない人が大きなつぼを持っており、お墓の下をがバっと開けました。
何をしてるのか、分りませんが。僕は珍しく、一言も言葉を発することなく、見守っていました。誰も、何も、言葉を使っていなかったから。
すると、知らな人がお墓の下に大きなツボをいれたのです。ただこのとき、つぼの中身より、お墓の下が開いたことより、つぼをお墓の下に入れたことよりも、僕はたった1つの疑問で頭がいっぱいでした。
「なんだろう、あの小さいツボ?」
大きなツボ、中くらいのツボが複数あったのですが。1つだけ明らかに小さいツボがあったのです。多分、僕の顔よりもずっと小さい。僕は、不思議に思いつつ、小さいツボを眺めながら、知らない人が大きなツボを入れるのを終始無言で見ていました。
それからの記憶は、しばらくありません。また記憶するようになったのは、4歳になる頃でした。
第四章 人の終わり方
時はながれ、小学生、いいや。中学生だったでしょうか。両親の仕事が忙しくなり、おばあちゃんが週末、家に手伝いに来るようになっていました。
その日も、おばあちゃんが家に来てくれました。部屋の中に、大きな石油ストーブと毛布が置かれるようになった頃だったと思います。
おばあちゃんが、こんな話をしてくれました。
「おばあちゃんはね。ゆーちゃんのおかーさんの他に子供がいたんだよ。」
「え?そうなの?」
僕が、なんでと言うよりも先におばあちゃんは口を開きます。
「おばーちゃん、しんおじさんの後に妊娠したんだ。」
「でもね。リビングでご飯を食べる時、おばーちゃん、しりもちついちゃったんだ」
「病院にいったらね。その子、お腹の中でしんじゃってたんだ」
「本当だったら、ゆーじって名前を付けていたんだけどね」
…その目は、どこか、知らない世界を見ているようでした。
「だからゆーちゃんのおかーさんを生むときは、すごく気を付けたよ」
おばあちゃんは、下手っぴな笑顔で僕にいいました。
その瞬間、気まずいとか、何を言えばいいのか、なんてそんなことを考えるより先に。頭のギアが何段階も急激に上がりました。
朝日が立ち上り、一筋の光が照らすように。ずっと分からなかったなぞなぞが解けたように。熱を帯びるほど回った頭がスーッと、澄み渡りました。気付けば、脊髄で声を出していました。
「ああ!だから、お墓の下に小さいツボがあったの?」
おばあちゃんは、目を丸くして、あんぐりと口を開けてから、ぽつんと呟きました。
「なんで知っているの…?」
僕は、答えようとしました。答えようとした、その瞬間。全て理解しました。全ての記憶が、情報が、濁流のように押し寄せて、映像のトンネルを通るような、刹那。僕は、1つの結論にたどり着きました。
ああ。
そうか。
あのとき。
おじいちゃん。
火葬されたのか。
僕は、3歳の時、人の終わり方を知りました。
おわり
なかなか、重い話でしたね。でも、これマジであった話です。僕が本当に体験した昔の記憶です。まったく、誇張も極端な表現もしていません。
人の記憶って危険を感じた時から始まるらしいですね。危ないから、学習して、気を付けないとって。だから、最初の記憶は驚いた記憶。そして次は…。
3歳でも、人の終わり方を本能で理解していた。だから、覚えていたのかもしれませんね。だから3歳のそれ以降の記憶が空白で、4歳からの記憶しかないのかもしれませんね。

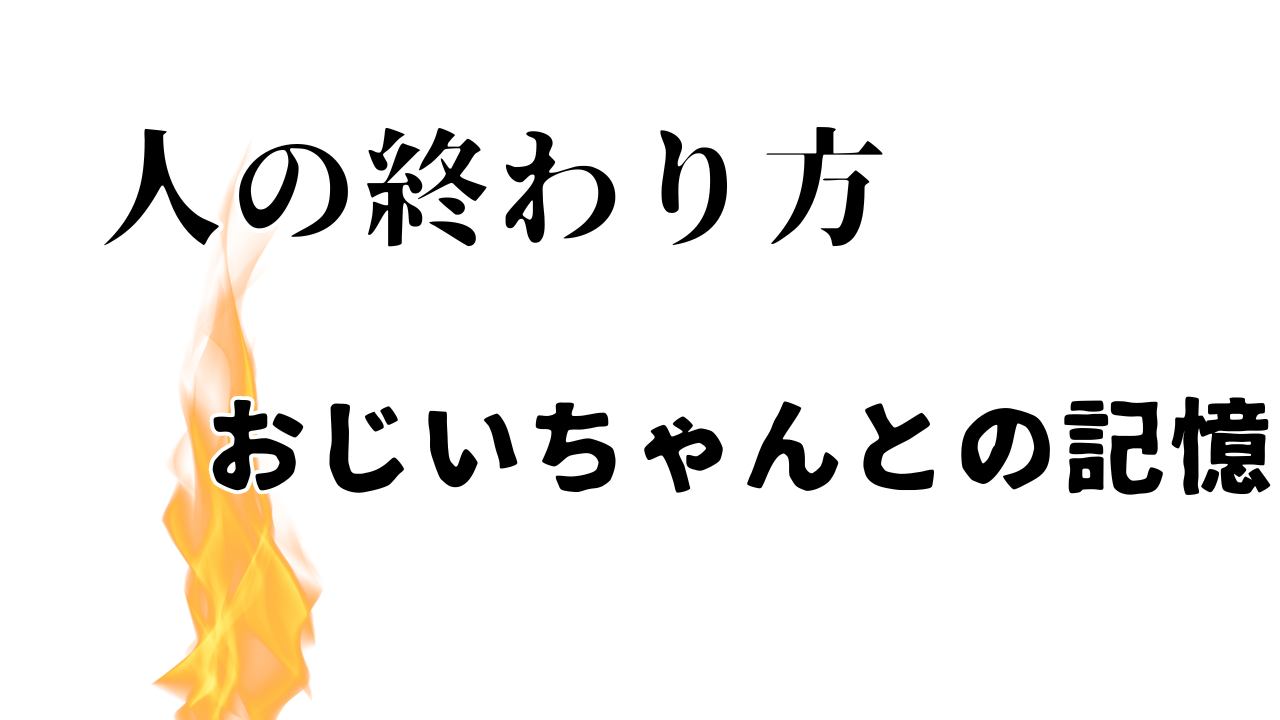


コメント